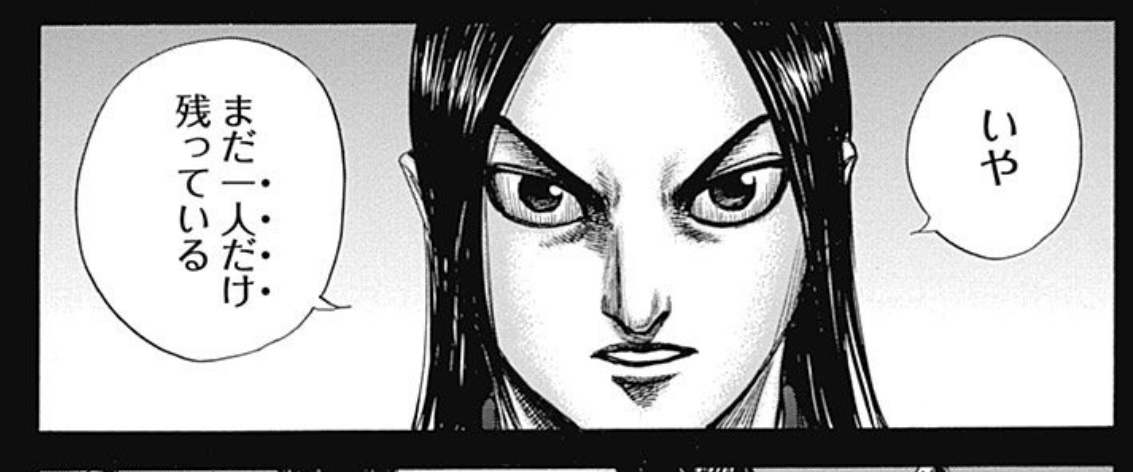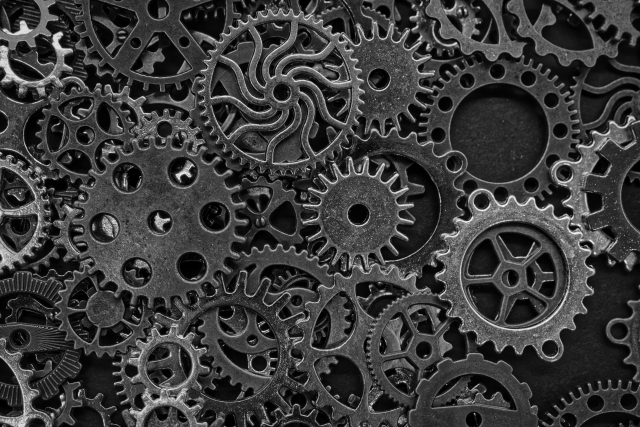部下育成の極意 | 失敗から学んだ「育て方」の具体例
初めて部下を持った方へ。
部下を持ちながらも育成に悩む方へ。
そんな方へ。
私が実践してきた、部下の育成について、成功体験はさることながら、失敗談も交えて、詳らかにしていこう。
育成には、正解はない。
ある程度型化された情報は存在する。ただ一方、同じ人がいないことと同様に、全く同じ育て方が望ましいことはない。
1. 部下育成に悩む全ての上司へ
まずは、「育成に悩む」全ての人へ。
なぜ人は育成に悩むのだろうか。
そして、なぜ育成しないといけないのだろうか。
正直私は、マネージャーになりたての頃は、わからなかった。
「人」は勝手に育つものだと思っていたし、「人」についても正直理解していなかった。
そんな私の失敗談を元に、「部下の成長と育成」について記述していこう。
– なぜ部下が成長しないのか?
結論1つである。
それは、「上司が部下のことを理解していないから」である。
至極真っ当なことである。
人の成長を促すためには、その人のことを理解する必要がある。
- どんな成長を望んでいるのか
- 何が得意なのか
- 何が好きで、どんな特徴を持っているのか
まずは、ココを理解するところからである。
「部下が成長を望んでいない場合もあるのでは?」という話もある。
しかし、それは、結局部下を理解していれば、「その部下に成長を促さない」という手法を取ることができる。
結局は、マネージャーないしは、上司次第なのである。
成長しないことを部下のせいにしてはいけない。人の上に立つものは、他責にせず、原因自分論で考える必要がある。
– なぜ部下を育成する必要があるのか
結論、成果を出す必要があるから。
この結論は、会社に勤めている人に限るかと言われると、それに限った話ではない。
組織に属していれば、必然と要するものである。
もちろん1人で事業を運営していて、その後拡大の必要もない。
組織化するつもりもない。という場合は除く。
しかし、それ以外の場合において、成果を残すうえ育成は非常に重要である。
なぜか。それは、成果を残すには、「人」が必要であるから。
その人をどのようにして、用いるのか。
★採用 or ★育成
の二つである。
ビジョナリーカンパニー2〜飛躍の法則〜において「誰をバスに乗せるか」という話があるため、実のところ重要なのは、「人を採ること」である。
ビジョナリーカンパニー2はこちら
一方、バスに人を乗せたら終わり、という話ではない。
その、バスの中でも役回りが必要であり、その役回りに合うように育成が必要なのである。
それは、バスに乗せた後に、その人と共に組織にとっての成果を出す必要があるためだ。
– 3年目の部下育成における失敗
私は、社会人5年目。会社の事業を管轄するマネージャーとして活動している。
小規模な会社なため、正直まだ、部下は10人ほども見たことがない。
しかし、その中で、3人の人間を挫折へ追い込んでしまっている。
そのうち一人は、退職代行を使われ、突然退職となった。
どんな失敗をしたか、述べていこう
1.本人のストレスを感じ取っているようで感じ取っていなかった
私が部下を理解していなかった失敗の1つは、本人のアラートを受け取れていなかったことである。
本人は、「全然大丈夫なんですけど、最近寝れないんですよね〜」と軽い感じで相談をしてきていた。
- 「寝れない」という原因
- 具体的にどのくらいの期間寝れてないのか
- 体にどんな支障が出ているのか
など、何も聞いていなかった。
意図的に無視して理解しようとしていなかったわけではなかったが、そこに気が回っていなかったのだ。
故にその数ヶ月後に、1週間ほど休暇を取ることになり、その後、部署異動によりストレスの少ないような仕事をやることになった。
2.本人のやる気を信じすぎて、大きな業務を任せた
2つ目は、本人が非常にやる気がある人だった。
どんどん仕事ができるようになりたいし、成長していきたい。と本人の口から聞いていた。
そのため、ひとつプロジェクトを任せることにしたが、
途中で責任に耐えきれず、該当プロジェクトは別の人を立てることになった。
最初の本人のやる気から判断したが、その熱意を信じすぎたことによる失敗である。
京セラの稲森さんが言っていたを思い出そう。
「熱意」x「能力」x「考え方」
上記のうち、どれかが欠けていれば、成果の最大化につながらない。
本人に「熱意」があったとしても、「能力」や「考え方」が成熟してないうちは、「責任」を与えすぎるべきではない。
ただし、「責任」を与えることで、人は成長するため、程よい責任で成長をさせていく必要はある。
3.キャパ以上の仕事を振っていた
元々、販売員として活動をしていた方が転職をして入社してくれた。
本人は、今までやったことがない業務ではあるが、今後の社会人として成長する上で、必要なことだといい、何でも取り組んでくれていた。
資料作成の基礎、スプレッドシートの関数、メールの基礎、意思決定の基準やプロセスなど、全てを事細かに教え、私の経験してきた仕事の基礎を徹底的に叩き込もうとした。
しかし、本人が体調を崩す。
また、「頑張りたい」という言葉を鵜呑みにしており、本人の状況や今後の理想的キャリア、特性、好きなこと、仕事における特性などの理解をしていなかった。
これもまた聞いていたつもりだった。
結果として、本人が体調を崩したまま、退職代行でご退職されることに。
部下育成における重要要素
愛を持って、未来を考え、心底理解に努めること
ここでは、どうやって育成すればいいのかという、瑣末なことを話したいのではない。
重要なのは、本当に相手を思うことだ。
部下のことを考えられないのであれば、「上司」になる資格などない。
ただし、ここで言いたいことは、「部下に迎合する」という話ではない。
相手のことを心底考えるというのは、「親になった気持ちで接する」に近い。
迎合することによって、組織の活動が動かないというのは、話がちがう。
あくまでも、成果を出すことを前提として、本当に相手と向き合えるか、が「育成」における最も重要な事項である。
2. 部下育成における失敗パターン
ここからは、育成において勘違いされやすい罠とそれによる失敗を簡単にまとめていこう
– 育成現場で起きる4つの典型的な失敗パターン
育成を簡単なものだと捉えている
部下の育成は、簡単なものではない。
太古よりおこなわれて、時代が変わろうとも実行されている「マネジメント」において、名著が出て、型が科学されている。
にもかかわらず、何人もの上司を苦しめている「育成」
型はあるが、正解はない。が故に簡単なものではない。
個人に合わせた「育成」が必要な故、育成は難しい
甘く見て、人を育てようとした際には、
後々、大変な目に遭うことになるだろう。
(もちろん、部下との相性もあり、たまたまうまく行く可能性もあるが、再現性を持って育成に取り組むこと自体は非常に難易度の高い仕事の1つである。)
自分の成功体験の押し付けをする
典型的な老害の象徴である。
自分が成功したことを盾にその成功を押し付ける上司もいる。
これほど、嫌な上司はいないだろう。
自分ができること、自分が得意なことが、相手も得意とは限らない。
その成功体験を押しつけ「俺は、こうやったらできた」というような育成は育成ではない。
相手の強みや特徴を理解して、そこを最大限に伸ばすことこそが育成の本質である。
部下が育たないことを自らの能力不足と捉えすぎること
先に書いたように、「部下の特徴や強み」を伸ばすことこそが育成である。
が故に、弱みの部分を伸ばそうとしても、限界がある。
その伸び悩みにおいて、「自分が全部悪い」「自分の責任で育たない」と考えすぎてしまう人もいる。
「原因自分論」は非常に良いことではある。
もちろん部下が育たないのは、上司が部下を理解していないという側面が強い。
しかし、本人の能力や根源、価値観にも限界があり、
そこは、上司自身の変数になり得ない。
定数において、原因自分論で捉えすぎることは育成における失敗の一つと言える。
育成が目的化してしまうこと
育成を目的化してしまうことも大きな失敗の一つである。
育成はなぜやるのか。
なんらかの「成果を出すため」である。
「育成=成果」と思っている人は、今一度考え直すことを推奨する。
(もちろん、育成することだけを求められている場合は、その限りではないが、その育成もその先になんらかの目的があるはずである)
本当の目的から、視座視界が離れ、目の前の育てるということだけにフォーカスしてしまうことは、本末転倒になるため注意が必要だ。
– なぜベテラン上司は部下を育てられるのか?
一概に正であるとは言い難いが、
先にも記述した通り、「人の数だけ育成の正解がある」が故に、経験してきた数が多ければ多いほど、育成パターンを経験し、再現性を積めるからである。
簡単な話である。
練習をたくさんした方が、うまくなるという話に等しい。
決して、長く働いているから上手にできるわけではない。
上司として、育成がうまくいっている人は、過去に何度もいろんな経験をしながら、人を育てたり、傷つけたりしながら、大きく成長してきているわけである。
「努力をしたものが、報われるとは限らないが、報われた人は、必ず努力をしている。」
決して、才能によるものではない。再現性を作るのは、絶対に努力である。
まとめ
ここまで、部下育成において、重要なことを記述してきた。
枝葉の話が重要なのではない。
なぜ、育成の本質を見極めることこそ重要である。
そのため、どうやったらいいかという具体的な話は、ここに記載をしていない。
次に書く記事で、具体的事例について詳しく記載していく。
忘れてはいけないのは、「自分の部下になってくれたことは、当たり前ではない」ということ。
育成には、「会社に対して」「部下に対して」双方に責任がある。
一人の部下を育てられないことによる損害は、「自分の評価」だけではないことは、肝に銘じておくべきである。
ここまで読んで、少しでも納得した方は次の記事も読んでもらいたい。